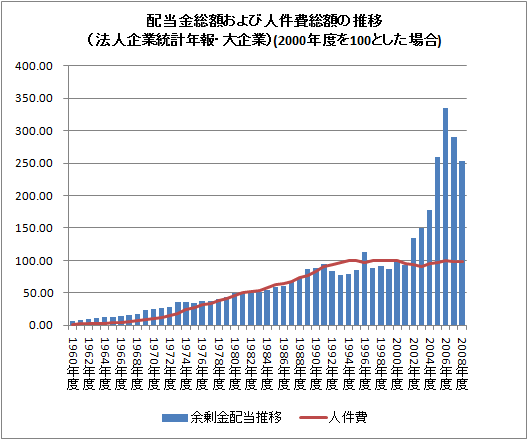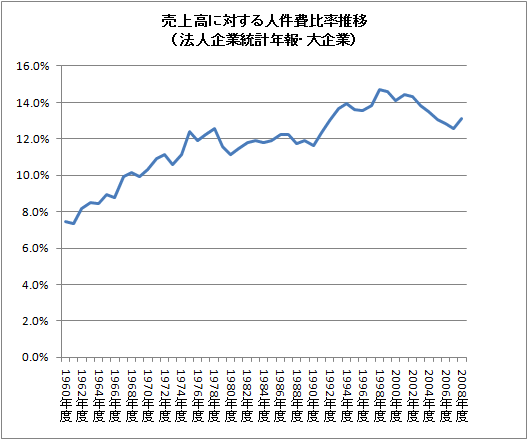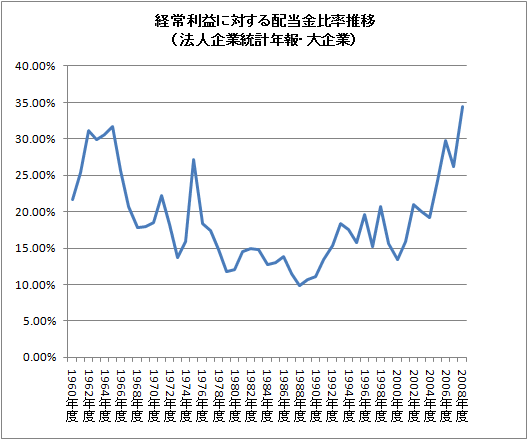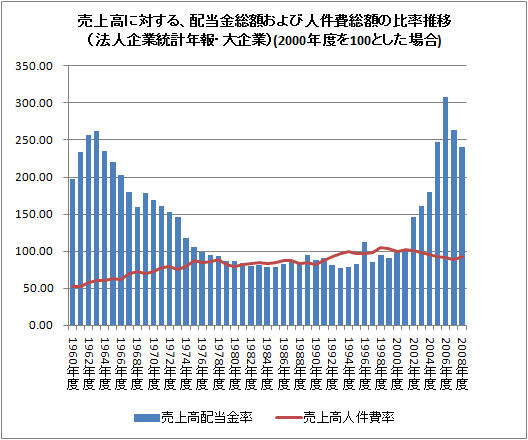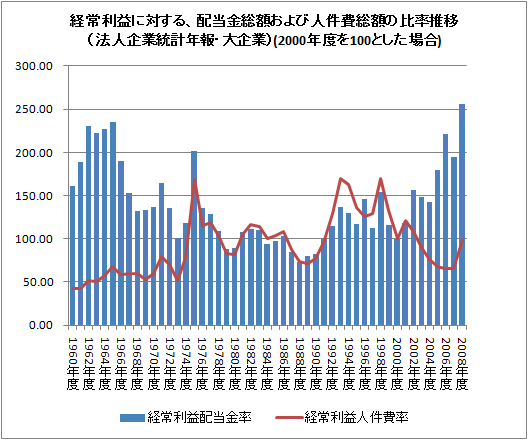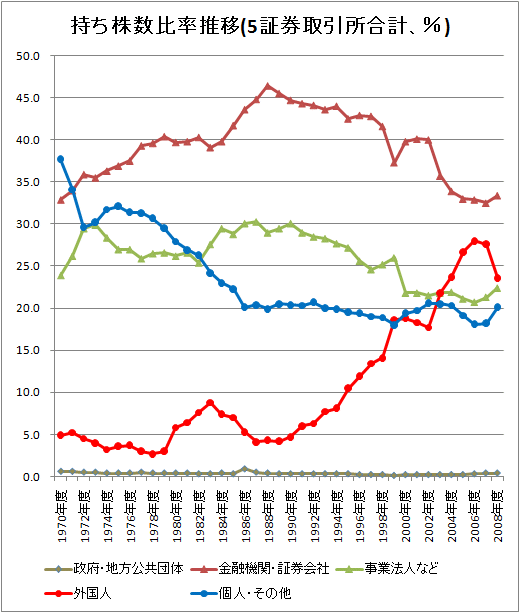このブログを検索
金融教育公開授業 - 知るぽると:金融広報中央委員会
www.saveinfo.or.jp/event/2011/11jugyo/pdf/setagaya.pdf
電車痴漢 被害者9割が通報せず、女性車両や防犯カメラ増を 警察庁・研究会
就活氷河期 自衛隊出身者が人事から高く評価されている
* * *
自衛官を採用する企業にそのメリットを聞くと、実に様々な感想が寄せられた。まずは、「リーダーシップ」である。ビルメンテナンス会社「東京美装興業」の人事部教育課長で、自身も元自衛官の上田正文氏が語る。
「自衛隊は集団生活。訓練もチームで行ないますから、自ずとリーダーシップが身につきます。例えばチームで行動する場合、1人でも脱落したら全体が失格、ペナルティを受ける。結果、各々が迷惑をかけないようスキルアップを図るようになる。
その一方で、初めての人の集まりでも各々の特性を見極め、役割分担をさせチームで成果を出すことが得意。自衛隊ではいつもリーダーを決め、個々人の任務を決めて動く訓練を行なっていますからね」
同社人事部長・山田勇氏が続ける。
「すべてがマニュアル化され、答えをすぐに求める昨今の若者と異なり、自衛隊員には自立して行動するサイクルが身についていると感じる。それも、こうした集団生活の背景があり、任務を中途半端でなく“完結”することが求められるからでしょう。弊社ではこの“任務”はビルの清掃などに当たりますが、誰も見ていないところでもきちんと仕事を果たしてくれる安心感がありますね」
この「任務完遂能力」は多くの企業で称賛されている。電気工事会社「六興電気」社長の長江洋一氏はこう話す。
「最近の学生はテストでの得点が60点以上で合格できるので、100点を目指さない。落第点でも後でレポートを出せばいい、という大学も多い。自ずと仕事に対する甘さが出てきます。我が社では新入社員に自衛隊体験入隊を課しているのですが、苦しい訓練を100%やり切る達成感を味わうことで、60点ではダメということを学ばせています」
また、自衛官の「マナーや身だしなみ」を評価する声も多かった。自衛官の再就職を受け入れている企業の団体、「入間基地退職者雇用協議会」の豊田義継会長はこう語る。
「最も期待しているのは、『言葉遣い』と『立ち居振る舞い』です。最近の若者はマナーを一から教えなければならないが、自衛官は訓練で身についている。外回りは当然のこと、内勤でも社内の人間関係を築く上で大変重要です。周囲の新人への手本となる波及効果も期待できるし、マナーについて何も懸念なく採用できると各社が口を揃えています」
※週刊ポスト2011年2月25日号
就活で体育会が有利なのは、昔も今も変わらない?続々開催される「体育会オンリー説明会」の内幕
就職活動「冬の時代」の昨今に限らず、選ぶのは主に企業の側なのだから。また、企業の求める人間像にも実のところ大きな変化はない。
「体育会学生の優位性」をそのホームページでもうたう株式会社アスリートプランニングは、「東京六大学就職リーグ」「関西七大学就職リーグ」と銘打った企業説明会を開催している。いわば体育会系学生に特化した、有名企業との出会いの場だ。
体育会系の学生が就活で有利なのは、今に始まったことではない。まず間違いなく体力があり、目標を定めた厳しい訓練を経験している。また、チームワークにも優れている(個人競技でもコーチや先輩が存在する)。
そこに「偏差値の高い大学」という条件が加われば、アタマもいい(悪くはない)ということなる。まさに、企業にとっては欲しい人材なのだ。ただし早い時期から企業説明に人が集まるということは、体育会系の学生たちですら、有名企業や第一志望の企業への就職には焦っているのだろう。
一方富士通は、2012年春入社の新卒採用で、スポーツや社会貢献、勉強、起業などで実績を挙げた「一芸に秀でた学生」の特別枠を3倍に拡大するという。これまでもスポーツ、社会貢献、起業などの経験を持つ学生は有利だったが、富士通の場合、そのための特別枠を設け、しかも「志望動機は訊かない」というあたりがユニークだ。「志望動機は関係ない」「ヒトとして優秀な人材なら何らかの役に立つだろう」という割り切った考え方とも言える。
日本経団連が会員企業など596社から回答を得たアンケートによると、企業が学生に求めるものは「主体性」「コミュニケーション能力」「実行力」なのだという。また、最近の学生には全般に「主体性」が足りなく、能力面では「既存の価値観に囚われない発想ができる創造力」が足りないとの回答が多かったという。
一芸に秀でることにせよ、主体性や創造力にせよ、それらはいつの時代も学生に求められていたものであり、新味はない。だが、選ばれる立場の学生にとっては難問だ。面接ではこれらのポイントをアピールしなければならないが、たとえ好印象を与えることに成功しても、より「秀でた」学生がいたら選ばれないのである。
就職活動における企業と学生との「ないものねだり合戦」は永遠に続くと思われるが、先述のように選ばれる側の学生が圧倒的に不利である。救いなのは、企業サイドも「ほとんど全ての面で優れた人材」または「一芸に秀でた人材」が、全学生のほんの一部であることなど、承知の上ということだろう。
(工藤 渉)
大企業の配当金と人件費の関係をグラフ化してみる。 上場企業の「外国人」持ち株比率: "
先の【日銀レポートによる「なぜ好景気でも賃金は上がらなかったのか」】で解説した、日本銀行関係者による研究レポート【賃金はなぜ上がらなかったのか? - 2002〜07年の景気拡大期における大企業人件費の抑制要因に関する一考察(PDF)】では、その推論を導くために多種多様の役立つ図表が展開されていた。今記事ではその図表の中から、大企業が株主に支払った配当金や人件費について、総売り上げや経常利益との関係を色々な形でグラフ化してみることにする。
データの大本は財務省のシンクタンク【財務総合政策研究所】の公式サイトで掲載されている、【法人企業統計調査】で確認できるもの。調査対象や条件などは【調査の概要】で確認してほしいが、原則的に資本金1000万円以上の営利企業を対象とし、資本金が大きなところは回答データを全部、小さなところは等確率系統抽出により抽出している。そして今回は掲載されているデータのうち、バックナンバーなども合わせ、1960年度分から2008年度分までについてグラフ化のための再入力を行った。
まずは日銀レポートにも掲載されている、売上高に対する、配当金総額および人件費総額の比率推移。
配当金総額および人件費総額の推移(法人企業統計年報・大企業)(2000年度を100とした場合)
景気後退のあおりを受けて直近の2007年度〜2008年度は配当金の額が落ちているが、それでも「額」そのものは今世紀に入ってから増加の一途をたどっている。一方で人件費総額は横ばいで推移している。【上場企業の「外国人」持ち株比率の変化をグラフ化してみる】や【外国人株主の増大が企業の「株主重視姿勢」を後押し!?】にもあるように、外国人株主の増加が「配当額増加」の圧力となり、企業がそれに応じたように見えること、そして【日銀レポートによる「なぜ好景気でも賃金は上がらなかったのか」】で指摘されているように、賃金が上昇しなかった一因を裏付けているようにも見える。
●売上や経常利益に対する比率で考えてみる
しかしこれらは「総額」であり、配当ならば1企業当たり、人件費ならば1人当たりを考慮したものではない。人件費ならば主に売上に、配当ならば経常利益との兼ね合いを考える必要がある。人件費は企業継続には欠かせない(人材そのものの維持が欠かせないから)から「費用」の扱いであるし、配当は利益の分配の一部であるから「利益の分け前」であり、費用よりも順位は低いからだ。
そこでまずは、「売上高に対する人件費」「経常利益に対する配当」それぞれの割合を求めてみる。後者について、本来の「配当性向」は純利益に対する配当の割合だが、それに近い値と思えば良いだろう。
売上高に対する人件費比率推移(法人企業統計年報・大企業)
経常利益に対する配当金比率推移(法人企業統計年報・大企業)
このグラフからは、
・1960年度以降、概して売上高に対する人件費の割合は増加している。
・利益に対する配当の割合は1960年代前半は大きく、以降は減少。2000年度以降再び増加し、1960年前半と同水準に。
などの傾向があることが分かる。
さらに参考データとして、「売上高」「経常利益」それぞれに対する、人件費・配当金の比率を算出し、2000年度の値を100とした場合の推移を示したのが次のグラフ。
売上高に対する、配当金総額および人件費総額の比率推移(法人企業統計年報・大企業)(2000年度を100とした場合)
経常利益に対する、配当金総額および人件費総額の比率推移(法人企業統計年報・大企業)(2000年度を100とした場合)
「経常利益に対する人件費」はやや乱高下していること、「売上高に対する人件費」は(前述の通り)ほぼ右肩上がりであることを除けば、1960年代前半と2000年以降には、奇妙なパターンの類似傾向が見られることが分かる。
●1960年代前半には何があったのか
「昨今の企業における人件費や配当の傾向」と似通っている「1960年代前半」には何があったのか。偶然だがマネー情報誌の【ZAi最新号(2009年10月号)】には次のような記述があった。
・1960年代前半、まだ日本の産業が不安定だった頃、投資家たちはトヨタやソニーのような企業ですら「10年後にはつぶれているかもしれない」と思っており、誰も株価の値上がり期待していなかった。
・実際、株価も額面の50円台からほとんど動かず、投資家の関心は配当に向いていた。10年後にはあるかないかもわからない会社だから、10年間でどれだけ配当を出してくれるか、という方が重要だった。
・しかし70年代に入ると日本企業の業績が右肩上がりとなり、投資家の関心は「配当よりも株価上昇」と移り変わり、配当を軽視する雰囲気になった。
つまり1960年代前半は、「投資家も企業も各企業の中長期的な未来にさほど自信が無く、企業は守りの姿勢、投資家は短期的な利益に重点を置いていた」ことになる。
先の日銀のレポートでも、賃金が上昇しなかった理由として「(主に外国人投資家の比率増大による)株主からの圧力上昇」以外に、「企業が直面する不確実性の増大」を要因として挙げていた。企業の中長期的な先行きに自信が無ければ、同じような状況だった1960年代前半と類似の傾向を見せることは十分にありうる。また「原材料などの仕入れ価格上昇」なども間接的に「企業が直面する不確実性の増大」を後押しする要因となるだろう。
--------------------------------------------------------------------------------
人件費や配当、売上高や経常利益について過去半世紀ほどのデータを参照した限りでは、
・人件費は
1.売上高に対しては一定割合で増加を続けている。
2.経常利益に対しては全体的には増加傾向。1990年代は大きく伸びたがその後下落し、再び上昇傾向。
・配当は
1.売上高・経常利益双方に対して「企業の長期的リスクが大きかった」1960年代前半は高め、以降低めに推移したが、今世紀に入ってから再び上昇。
などの傾向が見受けられる。
【上場企業の「外国人」持ち株比率の変化をグラフ化してみる】にもあるように、1960年代(記事上グラフは1970年以降だが、恐らく1960年代も大きな変化はないはずだ)に比べて最近の外国人投資家の持ち株比率が高いことを考慮すれば、1960年代前半と比べて配当に対する圧力が強く、今世紀に入ってから配当への重視率がやや大きくなっているのも理解できる。
企業も投資家も、1960年代前半に経験した
「先行きの不透明感・不安感」を
感じているのではないだろうかその点を除けば、日本企業は「配当に支払うお金を重視するあまりに人件費を削減している」のではなく(むしろ「売上」「利益」に対する配分率は増加している)、日銀のレポートでも指摘しているように「企業のゴーイングコンサーン(企業が将来にわたって永続的に事業を続け、廃業や財産整理などをしないことを前提とする考え方)への不安が高まり(そして投資家たちも同じ認識を持ち)、結果として似たような状況下にあった1960年代前半と同じような姿勢を取っている」のではないかと思われる。
これは過去のデータとの類似性を元にした推論に過ぎない。また、仮に正しいとしても、あくまでも一要因であり、他にもさまざまな理由はあるに違いない。しかしそれでも、少なくとも当方自身が納得の行く話であることだけは確かである。
先の【日銀レポートによる「なぜ好景気でも賃金は上がらなかったのか」】で解説した、日本銀行関係者による研究レポート【賃金はなぜ上がらなかったのか? - 2002〜07年の景気拡大期における大企業人件費の抑制要因に関する一考察(PDF)】では、その推論を導くために多種多様の役立つ図表が展開されていた。今記事ではその図表の中から、日本の上場企業の経営方針を変えた一要因とされる「持ち株比率」の推移をグラフ化した上で、外国人投資家の影響力の拡大を眺めてみることにする。
データの大本は東京証券取引所による【株式分布状況調査】で掲載されている、「長期統計」データ。このデータ中、「投資部門別株式保有比率の推移」を研究レポートに掲載されているグラフと同じような区分で仕切り直し、グラフ化したのが次の図。
持ち株数比率推移(5証券取引所合計、%)
1980年度前半に一度上昇を見せた外国人投資家の比率だがその後低下を見せ、1990年前半以降じわじわと上昇。特に2000年前後を境に(一度ITバブル崩壊でやや下げ基調を見せるも)大きく伸びを見せている。一方で事業法人や金融機関・証券会社などは持ち合い解消などの流れを受けて2000年前後から大きく比率を減じている。
個人の動きをみると、1970年後半から急速な減少ぶりを見せ、1980年後半からは横ばい。1990年後半からは「貯蓄から投資へ」の動きを受けてやや盛り返しの雰囲気があったが、投資先の多様化などもあり、再び下落。
……というのが日銀の元資料によるところまでだった。これらの流れから「上場企業における外国人投資家の影響力増加と共に、『利益の従業員への還元より株主への還元を優先しろという』圧力が強まり、企業の利益が積み上げられても従業員の手取りには反映されなかったのではないか」とするのがレポートの推測による一要因。確かにこの15年ほどの動きをみると、影響力は2倍強にまで拡大しており、(たとえ外国人投資家全員が頑ななまでに配当重視を声高に訴えるだけではないとしても)推論を裏付けるようなデータではある。
--------------------------------------------------------------------------------
一方、日銀レポートには無かった2007〜2008年度分のデータをみると、興味深い傾向が見えてくる。この時期はいわゆる「金融(工学)危機」で(現在進行中)、世界中の金融商品の価格が急落を見せた時期。「外国人投資家が換金売りを続け、それが日本の株価下落の大きな原因となった」と説明されているが、それを裏付けるように外国人の持ち株比率が急激な下落ぶりを見せている。他方個人などは比率を上げており、下落過程では少なくとも外国人らと同様の「投げ売り」はしていなかったことが分かる。
個人の株式購買意欲と資金がどこまで続くかは未知数だが、この傾向が継続すれば株主構成比率、そして企業と株主間のパワーバランスに大きな変化が生じる可能性は否定できない。企業に対するプレッシャーの内容が変われば、企業の経営方針にも変化が生じ、それが元で企業の従業員に対する待遇に動きが生じる……となれば、注目すべき流れではあるのだが。今後とも注意深く動向を見守りたいところだ
【消費税増税は雇用を破壊する。】: "【消費税増税は雇用を破壊する。】・・・オリーブの声
日本の消費税は、所謂、付加価値税である。
納税義務者は事業者である。
国税庁は、以前は「預かり金」と説明していたが、最近は「預かり金的」と表現している。
いくつか非課税とされている税目を除き、基本的に付加価値は、粗利益を指す。
消費税の原理は以下の数式で表される。(非課税適用を除く)
(売上ー仕入れ)*税率=消費税
消費税は、付加価値にかかる税金であり、構造的には消費される財やサービスに課税され、製造業者やサービス業者が代理徴収の形式をとる。
しかし【納税義務者は、前述の事業者】であり、消費者が毎年申告するものではない。
導入当初は外税であったが、2004年4月1日より総額表示に変わり、所謂、内税となった。
だがここで問題となるのは、大手の製造業者の多くは卸を経由して小売業に販売しているため、その段階では消費税は外税表示である。
一方、消費者に対する小売業者は、総額表示のため、この段階で消費税の実質的負担者は曖昧になっている。
国内総生産(GDP : Gross Domestic Product)とは、一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額である。
さて、消費税の原理からすれば、消費税は粗利益に掛かるから、損益計算上は最初に消費税分として預かり金的に処理することになる。
しかしもし事業者の売上が増えない状況に於いて、消費税率が10%に上がれば、自ずと事業者の実質的粗利益が減少する。
実質的粗利益が減少すれば、それは個々の事業者の収益力に無関係ではないものの、全体の賃金支払力や機械等設備投資力が減少する。
賃金支払力が減少すれば、所謂、雇用力が減少する。
あるいは、賞与や昇給が減少する。
すなわち損益計算上は、所得税も法人税も減ることになる。
なお大企業は、消費税を転嫁できているから困らない、がしかし、市場全体では実質的な付加価値が減少する。
その消費税が仮に10%となれば、税収は増えるが、その税収を仮にPB(プライマリーバランス)の使途や大企業の法人税減税に使ってしまうと、結論として国の生産力に大きな影響を与える。
つまり、消費税増税は更に雇用を破壊し、あるいは、賃金を押し下げ、勤労者所得を減少させ、社会保険の負担者減(給付減)を招く。
他方、輸出大企業は消費税還付が10兆円規模に拡大し、その大企業の株主の過半は外資であるから、配当金ガッポリである。
法人税の引き下げが行なわれれば、減税は増収であるから、これも配当金ガッポリである。
しかも大企業は前述のとおり消費税を転嫁し得る。
整理すれば消費税増税は以下のとおり。
1)国民は更に生活が苦しくなる。
2)消費税を転嫁できない中小零細は益々苦しくなる。
3)実質的付加価値の減少は、雇用を破壊する。
したがって消費税増税とは、国民と弱小事業者から搾取し、大企業に富を移転する天下りシステムの完成を企図するものである。
オリーブ拝
"